平成19年1月号
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
先日、子どもたちの登下校に付き添っていただいている「スクールガード」の方が教育委員会をお尋ねになってお話をされていかれた。おなかの中にたまっていたものを吐き出されたが、「なるほど」と思うことなので、ここで紹介させていただく。
その方は「朝、子供たちの登校に付き添っているが、子どもたちの集団登校の列の後ろから、中年の女性の方が乗っている自転車が来る。するとその女性はベルを鳴らし続け、子どもたちの横をスピードも緩めずに通り過ぎる。危なくて見て居れない。交通指導員も子どもたちに向かって『自転車が通るから道を空けて、気をつけて』と子どもたちばかりに注意するが、それでいいのだろうか。確かに子どもたちは3列になったりお話に夢中になったりしているが、安全な歩道上のことである。和気あいあい、多少の列の乱れが子どもたちにあるのは当然のことだ。ここは自転車の女性も子どもたちの横を通り過ぎるときは、それなりの配慮があってもよいのではないか。女性に注意することもボランティアのスクールガードの私としては、できないし・・・・。もし、子どもたちに接触して怪我をさせた場合、警察へ通報してもよいものだろうか?」と話された。よほどその女性にお腹立ちの様子であった。
状況を想定してみれば、ごく当たり前の風景である。後ろから自転車が来たら、誰もまず子どもたちに注意を促すだろう。子どもたちは少し寄り添って道を空ける。そして自転車がその横を通り過ぎる。自転車に乗っている人は、突然子どもたちが飛び出してくるといけないから、ベルを鳴らし続ける。どこでも見られる集団登校の一場面であるのになぜ?
多分、自転車の女性の少しの配慮のなさがそうさせているのだろう。子どもたちの横を通るときは、少なくともスピードを緩めてほしい。子どもたちの安全を守るスクールガードの切実な願いに違いない。できれば、子どもたちと接触しないように、そのときだけは自転車から降りて引いて通り過ぎていただきたいとも思っているだろう。なのに我が物顔に自転車優先とばかり、ベルを鳴らしながらスピードも緩めずに追い抜くのが当たり前のようにしている態度が許せない。ごもっともである。多分その女性は、全く気づいていないだろう。誰かがその女性にお話しなければならない。今後も続くようであれば私ども事務局のものが現場でお話をさせていただくことにしたが、当たり前だと思ってやっていることでもずいぶん他人に迷惑をかけてしまっているなんていうこともある。
できることであれば、通り過ぎるときに子どもたちには「おはよう。いってらっしゃい」そしてスクールガードには、「ご苦労様です。」の一言が言えるぐらいの「ゆとり」があれば、もっと温かい町になるだろう。
平成18年12月号
振り返ってみれば、もう師走。私個人にとってもなんともあわただしく過ぎてしまった1年でした。9月には、突然の入院・手術をし、健康について改めて考えさせられた年でもありました。そんなこんなで、12月になってやっと皆様へのメッセージを書き直すことができるようになりました。
さて、「日本教育新聞・Tesio」に記載されていました「特集・先生の胸のうち」という記事の一部を紹介させていただきます。首都圏の小中学校の先生100人へのアンケート調査の結果です。
「自分の指導している生徒は家庭教育が行き届いていると思いますか」という問いに対して、「はい」10人、「まあまあ」54人で過半数の先生が家庭教育の成果を認めてはいるものの、「あまり」36人、「いいえ」3人と家庭教育の不足を訴える先生が40パーセントもいるのはやはり心して受け止めなくてはいけないでしょう。「うちはうちなりやっているのよ。そんなの先生たちの勝手な言い分でしょう」と決め付けないで、「先生たちの声」に耳を傾けてください。いくつか紹介させていただきます。※印は私のコメントです。
「しっかり寝かせ、食べさせて登校させてほしいのですが、たったそれだけのことをおろそかにし、訳の分からないことを要望してくる親がおり、あきれ返ることが多いです。まずはことの善悪くらいしっかりと教えてほしいと思っています。」
※
お子さんは何時に寝ていますか? 朝食はきちんと食べて登校していますか? 登校時間になってもお母さんは寝床でグーグー、子どもは急いで菓子パンをかじって学校へ。それでも子どもに聞けば「朝食は食べているよ」。そんな生徒もいたっけ。それに、学校でのトラブルもまずは冷静に事実を聞くことが大切なのに、子ども言うことだけを聞いていきなり怒鳴り込んでくる親。そんな親に限って、先生が伝えようとする「事実」は決して受け入れない。子どもを信じてやることは大切だけれど、立派な子に育てるにはそれでいいのかな?
「働く母親が多くなるに従って、子どもへの心配りがなくなってきている。経験上、少ない時間の中で子どものことが後回しになってしまうこともあると思うが、今の母親は自分の事を優先に考えすぎると思う」
※
同感、同感。女性の社会進出は当然のこと。しかし、その影には大きな犠牲が伴っていることを認識していただきたい。両親が働く、子育ては行政で勤務が終わるまで肩代わりすればいい? とんでもない考え違いだ。どんなに行き届いた環境でも「親」の肩代わりなんてできっこない。子どもにとって「親」は「親」しかいない。子どもにとって何者にも肩代わりできない「親」を「親自身」は少々軽んじてはいないだろうか。子どもたちは「親」の認識の甘さの犠牲者となっているのだ。
「子育ては親が何らかの形で犠牲にならなければ、子どもの心の面が育っていかない。感謝の心や思いやりは、自分が無償の愛を受けたときにこそ、育てられる精神作用だと思う」
※
「個人懇談の時間ですが、勤務が5時半までなので6時からにしてください。」仕事と子どもの優先順位が違うだろう?「おかあちゃんは、忙しくっても何とかやりくりをつけて指定の時間に来てくれた。」子どもは親の愛につつまれ、感謝の心を抱く。親の小さな犠牲がとてつもなく大きなものを子どもに与えるということを考えていただきたい。今、全国的に話題になっている給食費を支払わない親、「今月は車にお金をかけたから給食費を払えません」??? 何を犠牲にしていいかわからなくなっている親たち、もちろん一部の親ではあるがついにここまで来たのか。
「家庭と一緒になってよい子育てをしましょう」というものも先生たちの声にはたくさんありますが、ここではあえて「先生たちの苦言」を紹介しました。私も学校現場にいたころから「親」や「家庭」の変化を感じていましたが、世の中の流れの中に改善するどころかますますひどくなる一方なのが現実です。改善策は・・・やはりすべての親に「子育て」の認識をしっかりしていただくことしかないでしょう。「学校の先生の一方的な言い分」とお腹立ちの向きもあろうかと思いますが、今一度考えていただくきっかけとなろうかと思い掲載したしだいです。
平成18年7月号 「オンリー・ワン」でいい? 「ナンバー・ワン」を目ざすことも大切!
今の若者は、なぜ職につくことを嫌がるのか、明治大学のある先生はこう説明された。「職につけば必ず他人と比較される。競争させられる。そしてもし自分が負けたら・・・それが怖くて職に就かないのです。そういう男の子が多くなってしまった。今の若いカップルでプロポーズするのは女性のほうからがほとんど。もし断られたらという事態が怖くてプロポーズできないということにも現れているのです。」 全員がそうとはいえないだろうが日ごろ大学生を相手にしている先生の言うことである。説得力がある。
今の若者たちが育ってきたのは、「差別否定」「みんな平等」こんな考え方に支配された環境である。運動会では大差がつかないように、同じような速さの子をそろえて走らせる。学芸会ではできるだけ主役を作らない。どうしても主役がいるときは入れ替わり立ち代り主役が交代する。挫折感を味わわせないないための配慮だが、思わぬ落とし穴も作っていた。「負け」を知らずに育った子が成長し、大人社会での厳しい現実、しかもそこでは親の力は頼れず自分の力でことを運ばなくてはならない。(もっともなおも親がしゃしゃり出るという実態もなくはないが・・・)。学校も過度に「平等」に気を遣い、保護者もそれを期待していた。
もっと昔、私の小さいころには学芸会の主役は一人。先生は、私にほんの一瞬の通行人役しかくれない。悔しい思いをしたこともあった。運動会では雨になることばかり祈っていた。足が遅いからだ。祈りは通じず徒競走ではいつもびり。3着までの賞品には無縁の6年間だった。小学生時代味わった屈辱感がその後の私にどう影響したかをきちんと分析して考えたことはないが、プラス面も結構大きいと感ずる。自分の弱点を痛いほど認識させられる。他人をうらやましくも思うが、でもそこでくじけるわけにはいかない。がんばるか、耐えるか、道は2つだ。もって生まれた素質はどうあがいたって変わるものでない。結局耐えることしか道はないことを自覚せざるを得なくなる。これが自分なんだと。でも自暴自棄になることはなかった。「みんなも弱さを抱えているんだ」とむしろ共感的に友達を見ることができるようにもなった。
良きにつけ、悪きにつけ自分を知ること、そしてそれは他人との比較でより明らかになる。良きは、伸ばし、生かし、悪きは、努力し、改め、かなわなければ耐え、決してそれ以上自分をおとしめることの無いようわが心を戒める。こんな経験を集団生活を通して繰り返し勉強していかなくてはいけない、その場が学校ではないか。「競争原理は教育の場にはふさわしくない。教育現場からそれを排除すべきである」という主張が正論のようにまかり通っているが現実の社会は「競争原理」で構成されている。子供たちが被害者になってしまう悲しい事件の中には、「競争」に対して耐性を育むことなく大人になった者が起こしていると推察されるものも多い。
さて今、学校では「自分のいいとこ探し」が盛んに行われている。「自己肯定」「自分の存在価値の認識」、自分に自信を持って、さらに伸ばしていこうというのものだ。これは個人個人には「差」があることを前提にしている。「何でも平等」が生み出した多くの害からの脱却である。しかし、もし学校が「自分のいいとこ探し」だけに終始した指導を行い「子供たち一人一人が自信を持って生き生きとしています」なんて喜んでいるとしたらとんでもない間違いを犯していることになる。「粒ぞろえの徒競走」の二の舞である。自分だけでなく「友達のいいとこ探し」もしっかりとしたい。その過程では自分はもちろん、友達の欠点も見えてくるはずである。そこでの指導も忘れてはならない。わが町の学校は大丈夫だろうか。
人には、おのずから差があり、互いにそれを認め合い、時には競争しあい、互いに切磋琢磨しながら、ともに伸びていく。教育は「個人差」を基本にすえたさまざまな取り組みをすることによって本当の意味での「平等な教育」と「生きる力を育てる教育」が展開されるはずである。
いよいよ、夏休み前の懇談会の季節がやってきた。懇談会の難しさを学校の先生たちは痛感しているはずである。
それは、「子供たちに自信を持たせ長所を伸ばすような懇談にしよう」という思いがあるからだ。結果、保護者にとっても耳ざわりのよい表現が多くなる。時には本当に伝えたいことが伝わっていないことすら起こっている。
「事実は事実としてありのままの姿を伝え、夏休みに何をするのかを具体的にお話しする」ことを、校長先生から先生方に伝えてあります。二学期制では、夏休みは前期の途中です。学習面でも今までの遅れがあっても夏休みの努力で挽回できます。昨年の例では、夏休み中に先生に言われたことに努力し、見事立派な前期の通知表を受け取った子が何人もいると聞いています。保護者の皆様も、お子様の長所とともに、取り組むべきことをきちんと先生から聞き出し、長い夏休み中にご家庭で気を配っていただきますようお願いいたします。
平成18年5月号 みんなで子どもたちを見守ろう。
「スクールガード」制度も2年目に入りました。通勤途中や、出張の帰りに登下校する子どもたちに寄り添っている赤いベストと赤い帽子姿をお見かけすると自然に頭が下がります。本当にありがとうございます。
昨年の実践の中でいろいろなご意見やご指摘もいただきました。いくつか紹介させていただきます。
まずは、スクールガードの方からのご指摘です。
★
多くの方がスクールガードに登録したはずだが、実際に活動していただいている方は限られているのではないか。家で赤いベストと帽子が眠っているのはもったいない。せっかく作ったユニホームだから有効にいかさなくてはいけない。
確かにそんなことも起こっているのでしょう。子どもたちの安全のために目立つ色にしました。たんすの中で眠らせないでベストや帽子の出番を多くしてやってください。お願いいたします。
★
あるお母さんに「親さんもスクールガードとして子どもの登下校の安全を見守っていただくといいのでは」と声をかけたら「私たちは忙しいから・・・。それに今
★
集団下校する子どもたちの態度が悪い。たまりかねて「そんなことばかりしていると校長先生に言うよ」と子どもに言ったら、そのあくる日その子の親から「子どもにそんなことを言うのは脅迫でしょう」となじられてしまった。どうすればいいのでしょう。
考えさせられることばかりですね。
でも、こんなお母さんもいるのです。スクールガードを引き受けていただいている保護者の方からの長い手紙の内容を要約して紹介します。
★
集団下校がいいと思っていましたが、子どもたちの様子を見ているとそうとばかり言っては居られないことがわかりました。集団下校中の「いじわる」をよく見かけるからです。言われた側はいたたまれず列からはなれ、ばらばら下校になってしまうのです。子供たちはとにかく「しつこい」「言葉が汚い」のです。「おばちゃんと一緒に行こう」とさりげなく離してやります。
また、こんなこともありました。2年生の女の子が自転車で通りすがった青年に「今の自転車の人きも〜い」といったのです。友達の同意を求めるためか何回も繰り返しました。幸いにも自転車の青年はそのまま通り過ぎていきましたが、「そんなことをいわれたら、悪い人でなくても殴りたくなるかもしれないからやめなさい」と注意しました。いつも子どもだけが純粋無垢の被害者とはとても言い切れないと思いました。
スクールガードとして近所の子どもたちにうっとうしがられないか心配でしたが「見守る姿勢」で取り組み、今は自分の存在が子どもたちの中に自然に入り込んでいるようです。子どもたちの方から学校での出来事を話してくれるようになりましたし、先生に叱られたことや、いらいら、悩みも語ってくれます。「こりゃ悪がきだ」と思える子も最近では視線を投げかけるだけで「やベー」という顔をして悪さをやめるようになりました。そんな子どもたちの変化を見るたびにやってよかったと思います。
このお母さんは自分の忙しい時間を割いて、スクールガードをしていてくれます。子どもたちの安全ばかりではなく、折に触れ多くの貴重な指導をしていただいているのです。現場での指導は必ず子どもたちの心に焼きついていくことでしょう。本当にありがとうございます。また、この方ご自身も、ご自分の子ども以外の子どもに触れることの意義や楽しさを掴んでおられます。
「時間がないから」とか「誰かがやってくれるから」と避けてばかりいるのではなく、やればやっただけの「収穫」はあるものですね。
最後にもうひとつ、お願いがあります。今広報無線で子どもたちの下校時刻の2時と3時に「散歩の呼びかけ」をしております。しかし、時には行事の関係で一つの学校だけ時間が合わないことも起きます。広報無線では「町内全体」に流しているため、それぞれの学校の状況に合わせると非常に煩雑で分かりにくくなります。臨時で下校時刻が変わった学校につきましては、「せっかくのご配意をいただいた散歩」が無駄になってしまいますが、よろしくご理解をいただきますようお願いいたします。
平成18年4月号 今年度はボチボチと書きます。
「広報ふそう」の紙面の1ページをいただいて、あれこれと思いつくまま書かせていただきました。これは教育長になってすぐにお願いをしたことであり、5年半続いたことになります。これをはじめたのは、町民の方に少しでも学校のことを分かっていただいたり、子育てのヒントに気づいていただいたり、時には人としての自分自身を振り返っていただき「心のある町」づくりに少しは役立つだろうと考えてのことでした。多くの町民の方から「毎月楽しみに読ませていただいています」とか「お知らせばかりの広報の中でほっとするページです」とか嬉しいお声をいただいてここまで続けてくることができました。
しかし、諸事情により「広報ふそう」の内容精選を求められることになり、広報担当者の続けたいとの意見に背いて私のほうから「教育長のページ」をご辞退させていただくことにしました。
ただ毎月とはいきませんが、このページでぼちぼちと書かせていただくことにしました。パソコンをお持ちでない町民の方には申し訳ありませんが今後ともよろしくお願い申し上げます。
平成18年3月号 「いただきます」って言っていますか?
「いただきます」って言っていますか?「給食や外食では不要」ラジオで大論争。1月21日、商業紙の朝刊(東京)の記事である。ざっとその内容を紹介しよう。
TBSラジオ「永六輔その新世界」で昨秋「いただきます」を巡る話題が沸騰した。きっかけは「給食費を払っているから、子供にいただきますを言わせないでと学校に申し入れた母親がいた」という手紙だ。番組でのやり取りを参考に、改めて「いただきます」を考える。
番組には数十通の反響があり、多くは「いただきます」を言わせないでほしいという母親の申し入れに否定的だった。あるリスナーは「私は店で料理を持ってきてもらったときに『いただきます』と言うし、支払いのときは『ごちそうさま』と、言います。立ち食いそばなど作り手の顔が見えるときは気持ちよく、よりおいしくなります』と寄せた。
一方母親のような考え方は必ずしも珍しくないことを示す体験談もあった。「食堂で『いただきます』『ごちそうさま』と言ったら、隣のおばさんに『何で』と言われた。『作っている人に感謝している』と答えたら『お金を払っているのだから、店がお客に感謝すべきだ』と言われた」という。
また申し入れを支持するものも数通あり、学校で手を合わせることに『宗教的行為だ』という疑問を投げかける人もいるという。
永さんは、中華料理店を営む友人の話を紹介した。その友人は「いただきます」と聞くとうれしいからお客さんの「いただきます」の声が聞こえたらデザートを無料で出すサービスをした。後日サービスを後悔していないかと尋ねたら「大丈夫です。そんなにいませんから」と言われたという。
新聞記者が直接伺った永さんのコメントも紹介しておこう。
(給食費を払っているという理由についてどう感じましたか)
学校給食で「いただきます」を言うことへの抵抗は、以前からありました。それは両手を合わせる姿が特定の宗教行為、つまり仏教に結びつかないかという懸念です。宗教的なことを押し付けるのは僕も良くないと思います。でも「いただきます」という言葉は、宗教に関係していません。自然の世界と人間のお付き合いの問題です。
「お金を払っているから、いただきますを言わせないで」というのは最近の話です。命だけでなく、お金に手を合わせちゃう。会社を売り買いするIT企業や投資ファンドにも共通点があると思います。話の発端になった母親は「いただきます」を言うかどうかを、物事を売る、買うという観点で決めているのでしょうね。売り買いはビジネスですから、そこに「ありがとう」という言葉は入ってきません。「ありがとう」に準ずる「いただきます」も入ってこない。ただ、そういう母親がいることも認めないといけないと思います。
(永さんは、どういう意味合いで「いただきます」を?)
「あなたの命を私の命にさせていただきます」のいただきます。でも僕は家では言ったり言わなかったり。ましてや、他人には強制しません。絶対言わなきゃいけないとは思いません。きちんと残さないで食べれば、「いただきます」といって残すよりいいと思うんです。
貧しい国には飢えて死んでいる人がいる。日本で残して捨てているご飯があれば、助かる子供たちがいっぱいいる訳でしょう。食べ物を大切にできているかどうか。言わないのが「ひどい」と反対することではないと思います。
(言っても言わなくてもいいと?)
普通に会って「こんにちは」、別れるときに「さようなら」。何かの時に「ありがとうございます」「すみません」「ごめんなさい」という、普通の会話の中に「いただきます」も当然入ってくると思うんです。特別に「みんなで言おう」というのはおかしい気がします。言っても言わなくても、大声でも小声でつぶやくだけでも、思うだけでもいいことにしましょう。《以上新聞記事から》
さて、皆さんは「いただきます」について、また、これらの意見についてどう思われますか。
学校では、食に対して、また作ってくれた人に対しての感謝の気持ちをもつことを教えている。それを表す行為として手を合わせ「いただきます」や「いただきました」あるいは「ごちそうさまでした」を言わせている。また、習慣として定着している手を合わせる動作や、「いただきます」の言葉を伝えていくことの大切さも考えての給食風景となっているわけだ。当然手を合わせることに「宗教」の意味合いはまったく含めてはいない。「宗教行為」と考えることのほうが、大人のこだわりを子供たちに押し付けているようでもある。もちろん強制的に行わせるものではないので、それにこだわるのであれば、個人的に手を合わせなければよい。
私もレストランでは、運んできた店員さんに「ありがとう」、店を出るときには「ごちそうさま」と言う。お金を払っているからとかレジ係の人が作ったのではないのにと思う人には奇妙に感ずるかもしれない。そればかりか、私は、店でものを買い、レジでおつりを渡されたり品物を渡されたりするときも「ありがとう」と言ってしまう。店員さんと私の「ありがとう」が飛び交うことになる。「あれ、変かな?」と思うこともあるが、私自身「ありがとう」という言葉を言うことによって気分がいいのだから、まあいいかなんて思っている。
平成18年2月号 鬼は外!
昨年、小学生が相次いで殺害を受けるという本当に痛ましい事件が起きた。広島の事件は、「悪魔」ともいえる外国人による犯行であり、栃木の事件は現時点(一八年一月初旬)では犯人像さえ浮かび上がっていない。京都の塾の事件では、若い講師が犯行に及んだ。「日本は安全な国ではなくなった」いや、「日本という国と日本人そのものが変化してきている」という現実をたたきつけられた。
日本も多くの外国人とともに生活する国になった。もちろんほとんどの外国人は、善良な人たちである。しかし、そういう人に混じって今回の事件の犯人のように、現地でも危険として扱われている人物が巧みな手を使って日本に潜入している。自販機あらし、空き巣狙いなどを目的に「平和ボケ」「安全ボケ」の無防備な日本人をターゲットに日本に乗り込んでいる連中もわんさかいるという現実を心を引き締めて受け止めなくてはならない。
日本人の変化は、目で見えないだけにもっと恐ろしい。あどけない子供たちに手を出す「鬼」がやたら多くなっている。
昔は大人の世界と子供の世界がそれぞれ存在し、子供は子供の世界で、大人は大人の世界で生活していたように思う。大人社会と子供の世界の境界線ははっきり引かれていたのだ。大人も子供の世界にはむやみに立ち入ろうとはしなかった。子供の喧嘩には「子供同士のことだから」とよほどのことでない限り親がかかわろうとはしなかった。大人にとって子供たちは子供の世界に住む「別人種」であるから、怨むとか危害を加えるなどという対象にはならなかった。
子供の側から見ると、自分たちの知らない大人の世界は憧れであり、早く大人になりたかった。少々背伸びすると「生意気だ」と手厳しく叱られもした。未知の世界にいるというだけで大人は大きな存在であった。だから大人にたてついたり、ましてや大人をからかったりなどできるはずがなかった。
それが今ではどうだろう。おやじ狩りをする中学生、注意されると反抗的な言葉を返す小学生。大人に対する恐怖もなければ敬意を抱くなど微塵も感じられない。大人は大人で「たかが子供のいうこと」と思えなくなってしまい、憎悪の念を子供にも募らせてしまう構図も出来上がってしまった。
今の子供たちにとって大人は、理想や憧れ、尊敬の対象とはなっていない。テレビなどマスメディアを通して、情報は大人と子供の区別なくどんどん供給されている。大人の世界は丸見えであり、もはや胸躍らせる存在ではなくなっている。
テレビ番組の中で、子供たちに有害な性描写や暴力シーンにはフィルターをかけようという動きがやっとでてきたが、当然のことながら通常のドラマやニュースにはフィルターはかからない。しかし、そこにも本当は子供たちには見せたくはない大人の世界があふれている。
大人を尊敬できなくなってしまった子供と、大人としての尊厳や大人であることの自覚をもてなくなってしまった大人の増加、力の弱い子供が被害者になってしまうような事件が起きてしまうのは必然ともいえるのではないだろうか。
・・・・うーん。どうすればいいのだ。この流れは変えられるのか?いやいや変わらないだろう。では、子供たちに「大人を尊敬すること」を叩き込む?それは無理だ。尊敬に値しない大人を現実に見ているのだ。むやみに大人を信用しようものなら殺されることもある世の中だ。
こうすればいいという結論なんて簡単に見つかるはずがない。が、現実は現実として、はっきりと子供たちに考えさせ、どう自分をコントロールしていくか理性的に行動する訓練を積み重ねることだろう。その子たちが大人になったとき、少しはよい方向に変化することが期待できる。そのときまで、大人たちも、子供たちから尊敬されるような大人であるよう自分を磨き続けてほしいものだ。子供の世界に踏み込む「鬼」がいてはならない。
この記事に対して「悪魔ともいえる外国人による犯行云々という一文は外国人=悪魔というイメージを読者に与える。このような暴言を吐く者がわが町の教育長であるというのはまったく遺憾だ。この不適切な発言について次号にてお詫びの掲載を求める」という内容の抗議のはがきをいただきました。
「広報ふそう」は、前月初旬に原稿の締め切りがされます。したがいましてはがきをいただきました時点では、3月号への記載はできませんので、ここで「お詫び」をさせていただきます。
ご指摘をいただきました点につきまして、私なりに配慮したつもりではありますが、誤解をいただくような表現をしましたことに対してお詫び申し上げ、改めて全文をお読みいただき、本旨をご理解いただくようにお願い申し上げます。
この記事を書くとき、どのように表現しようかと迷ったのですが、犯人自身が「そのとき私に悪魔が入ってきた」と供述していると報道されていましたので、本人の言葉よりあえて「悪魔」という言葉を引用しました。また、ご指摘のような誤解をさけるためにも「もちろんほとんどの外国人は、善良な人たちである。・・・・」という私の気持ちを続けさせていただきました。また、「日本人の変化は、目で見えないだけにもっと恐ろしい。」と、決して外国人だけを特別扱いしていないこともお読み取りいただければ幸いと存じます。当たり前のことですが、世間で使われる「外人」という言葉を用いず「外国人」と表現させていただくことにも配慮したつもりです。しかし、内容が内容なだけに、抗議をいただいた方のみでなく、外国人のかたがたや私たち日本人の大人や子ども、さらには、マスメディア関係の方にとってもそこだけを読めば確かに不愉快な気持ちを抱かせる部分も多いと思います。この点につきまして深くお詫び申し上げます。
平成18年1月号 皆さん今年もがんばりましょう
何か変だなあ。いきなりごめんなさい。まずは新年のご挨拶を。あけましておめでとうございます。
さて、何か変だなあ のことですが・・・・
電車の車掌さんのアナウンスである。その車掌さんは、電車乗り換えの案内はもちろん車内での携帯電話の使用禁止のことなどをこと細かく親切にアナウンスされていた。そして最後に「大変混み合いましてご迷惑さまです。あとしばらくのご辛抱をお願いします。」
「えっ、『大変混み合いましてご迷惑さまです』?これでいいのかなあ。」確実に間違いと言い切れるほどの確信も無いが何か変だと心に引っかかった。
電車を降りてからも歩きながら一生懸命考えていた。確かに、混み合っていて乗客は苦労している。そのねぎらいの意味を込めての「ご迷惑さま」である。車掌さんの思いやりがひしひしと伝わっては来る。が、どう考えても車掌さんの言葉としては、ちょっとぴったりしないのではないか。お客様に快適な状況を作るべく努力をすべきなのは経営者である。車掌さんはその会社の従業員であるから乗客に対しては経営者側としての言い方をすべきだろう。「混み合いまして、ご迷惑をおかけしております。あとしばらくのご辛抱をお願いいたします。」これなら違和感無く耳に入ってくる。「ご迷惑さま」という言葉の中には「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」という意味がこめられているようにも感じるが、ここははっきりと立場を明確にした表現が使われるべきであろう。
また、別の車掌さんのアナウンスを聞いてのことを紹介しよう。アナウンスひとつにも人柄が伝わってくる。昨日の電車の車掌さんのアナウンスは実にすばらしかった。ゆっくりはっきりと、一音一音明瞭な発声で案内をしていた。声もいい。かつてNHKのアナウンサーにこういうしゃべりの人がいた。この車掌さんはどんな人だろうか?きっと自分の仕事にプライドを持ち、生き生きと車掌業務をこなしているに違いない。車内を回ってくるときに会えるはずである。と、勝手に車掌さんのイメージを描いていた。そのときが来た。「えっ、この人があのアナウンスの人?」なんと車内を歩きながらの案内は、小さな声で口ごもるようにもごもごとやっているではないか。あまりのギャップにびっくりするやら、あきれるやら。でも遠ざかる車掌さんの後姿を見ながら、「きっとこの人は、シャイなんだ。マイク相手には堂々とものが言えても人前に出るとせっかくの自分の力が発揮できなくなってしまう。それでも車掌という仕事をこなさなくてはいけない。がんばれ!」勝手な憶測をしながら車掌さんの背中に応援のエールを送っていた。
どんな仕事でも大変なんだ。特に人と接する仕事となればなおさらのことである。自分の一言一句、一挙一動がその場で評価される。考えれば怖いことである。でもこの2人の車掌さんのように、自分の仕事を一生懸命やっていることが伝われば、少々のことはかえってその人の人柄として好意的に感じられる。
さあ皆さん。新しい年の始まりです。今年も一年、自分の仕事を誇りに思い、力いっぱい頑張りましょう。
12月号 北九州で(
「ハロー エブリワン・・・・・」九月八日、那珂川中(三百七十人)の一年三組.英語の授業で教室に英語の単語が響いた。教室の一番後ろで、生徒とともに懸命に唇を動かす藤悦子さん(八二)」は、時にはうなずきながら、目は教科書と教師を交互に追っていた。
西日本新聞に去る九月十一日に掲載された記事の書き出し部分である。もちろんこの記事には、「
と、わが町の取り組みが好意的に紹介されている。
続いて九月十八日、日曜日の「教育欄」には、「ゆとり教育を追う。町民聴講生 学ぶ意欲が素晴らしい」というタイトルの記事が掲載された。手前味噌で恥ずかしい思いもするが、原文のまま紹介をさせていただこうと思う。
「これはいただきだ」。 町民が児童生徒と一緒に授業を受けるー先週(十一日付)の教育面で、 テレビには「大阪の小学校だったと思う」(河村さん)が、おばあちゃんが四年生のクラスで児童と一緒に勉強している映像が流れた。小さいときに十分な教育が受けられなかった高齢女性が、実に楽しそうに授業を受けていた。学校長の裁量による一小学校の取り組みだった。河村さんは、即座に「町として取り組もう」と決断する。 学校を地域に開くことになる。町民の生涯学習に役立つ。年長者と子どもという異なる世代の心の交流が生まれそうだ。先生には負担かもしれないが、逆に緊張感を持って授業ができるのではないか。「いいことばかりだ」と〇一年秋、小中学校長会に正式提案した。 すんなり導入が決まったわけではない。前例がなく、学校現場に戸惑いが広がった。特に小学校は学級担任がすべての教科を教える仕組みで「部外者」を学級に入れることに教師の抵抗感もあったという。 だが、実際に始まると、そうした心配も消し飛んだ。 聴講生は英語や数学・算数、社会、音楽など選んだ教科の授業を受けるが、のみ込みが遅い分、予習復習は欠かさないなど「学ぶという熱意、姿勢が素晴らしい(河村さん)のだ。こうしたひた向きさが若い教師に感動を与えないわけがない。子供たちの学習意欲の向上にもつながっているという。 もちろん、聴講生は子供らとの交流も楽しんでいる。昨年から継続して聴講している町民が「この制度は町の宝」と言ったという。河村さんは「聴講生自身が制度の価値を分かってくれている」と自信を深める。 町民聴講生制度の導入には、新たに人もカネも要らない。特別の授業をするわけでもない。九州初導入となった
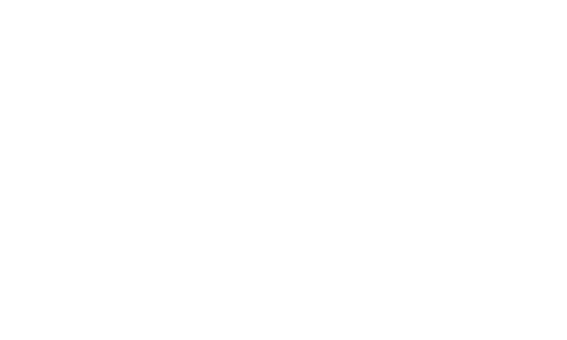
これまでも町民聴講生制度については、北海道から九州までの各地から、視察や資料の取り寄せなど多くあったが、実際導入したという連絡はなかった。いいことづくめのこの制度の価値を理解できても、学校の協力が得られず実現できずにいるのだろうと推察する。しかし、
福岡、博多といえば、辛子明太子が特産である。私の大好物である。日本人に好まれる明太子は大変な苦労の末に作り出されたものだという。貧困生活の中でやっと編み出した製法。特許もとらずそれを隠さず広めたという立派な人のおかげで、今私のようなものも口にすることができる庶民的な食べ物になっているのだそうだ。感謝感謝。そのお礼を、聴講生制度でさせていただこう。
聴講生制度の総本家として、18年度の聴講生の数が多くなることを期待している。
募集については、年が明けましたらお知らせしますので、ふるってご応募ください。(近隣市町の方も希望があれば聴講できます)
11月号 マナーは人の為ならず
過去のこのページに、スーパーマーケットでの出来事や、通勤途中の電車の中で感じたことなどよく書いてきた。スーパーには気取った買い物客はいないし電車の中ではあんぐり口をあけて熟睡なんていう姿もちらほら。どちらも無防備状態、本質を包み隠さず自分をさらけ出して行動しているからこそ、今どきの世の中がよく見える所でもある。
さて、今回もスーパーでの出来事を。私のお尻に後ろから来た主婦の押すカートがぶつかったのである。「痛っ!」思わず小さな声を出してしまった。当然間髪入れず「すみません」と声が聞こえるべきであるのにそれがない。もう一度わざとらしく大きな声で「痛っ!」と叫んでみた。そこで改めて後ろを振り向くと何食わぬ顔をしてカートの向きを変えようとしているご婦人の姿が目に入った。もう我慢の限界。「ごめんなさいの一言ぐらい言ってもいいでしょう。」当のご婦人は、たかがカートが少しぶつかったぐらいと思っていたのかも知れないが、私の怒った言葉に誘われ「あっ、ごめんなさい」と口を開いた。私は、物分りのいいおじさんを決めこんで「ハイ」とだけ返事をしてその場を立ち去った。
でも、私が「ごめんなさいの一言ぐらい・・・」と言った時の、ご婦人の表情は何だったのかその後もずっと気になった。恐縮や思わぬ事態に緊張してとかで見せた表情ではない。口元に笑みを浮かべて「ごめんなさい」なのだ。照れ隠しなんだろうか。確かに怒った顔よりはましだが少しは申し訳けなさそうな表情というものがあるのではないだろうか。ひょっとしたら彼女のほうが一枚も二枚も上かもしれない。「このオジイが大して痛くもないのにオーバーに。ここは、やんわりと・・・」
今回も、またまたどこかすっきりしないものが残ってしまった。
話題を変えてもう一つ。
「どうしてこんなものがここに?」明らかに客の心変わりで、一旦かごに入れたものを棚に戻したのだろうと思われる商品を見かける。中にはとんでもないところに戻されているものがある。肉や魚などの生鮮食品のトレイが乾物売り場にあったりするのだ。肉の品質の低下はもちろんだが、肉のトレイにくっついていた海苔も買う気がしない。「だれにも迷惑をかけていないし、面倒だから・・・・」きっとこんな安易な気持ちでいるのだろうが、しばらくの間放置されていた生鮮食品が店員さんによってもとのケースに納まり売られていく。客は「知らぬが仏」。でも知らずにそれを買わされているとなれば気分のよいものではない。消費者同士、互いに迷惑をかけないようマナーは守ろう。明らかに鮮度が落ちていれば商品としての価値はなくなる。店に損害を与える行為でもある。
また、こんなこともある。量り売りの肉屋さんで買ったビニル袋入りの肉が、トレイの並んだケースに一つだけ置き去りにされている。お値打ち品を見つけて心変わりをしたのか、急な献立変更でいらなくなったのか、量り売りの肉屋さんまで戻って返品すればことが済むのに面倒くさいし恥ずかしい。いずれにしても身勝手な人もいるものだと店主でなくてもあきれてしまう。もちろん店の人は「お客様第一」だから文句は言わない。
誰からも何も言われないから許されるのではなく、何も言われないからこそ自らを律しなければいけないことが私たちの周りにはたくさんある。それをするのが日本人の美徳であり、互いの気持ちよい生活の基盤になっていることは今も変わりないはずだが・・・・・。
平成17年9月号 ムシと子どもたち
「オーシンツクツク、オーシンツクツク」木立でのこの大合唱、渓流に竿を垂れる時には、「カナカナカナカナ・・・・」蜩の声に秋の到来を知る季節でもある。
セミといえば我が家の庭の木にも、毎年多くのアブラゼミが止まり、声の大きさを競うがごとく鳴いていたものだが今年はさほどでもなかった。緑が少なくなったためか、あるいは、気候の変動が影響しているのか、いずれにしても好ましくない状況であることは間違いない。セミやトンボ捕りに忙しい子どもたちの夏は遠いところに行ってしまったのかもしれない。
とはいえ、子どもたちの虫好きは、いつの時代も変わらない。が、今は、虫はデパートやホームセンターの商品になっている。数年前までの国産のカブトムシやクワガタムシに代わり、今年は漫画の影響もあって、外国産の大きくて立派なカブトムシに人気が集まっていると言う。もちろん輸入業者がいる。東南アジアへ発注しても、現地でも捕獲しすぎてなかなか捕まらないようになっているとか。日本の子どもに起こった大ブームが、間違いなく東南アジアの森林の生態系を崩している。
虫好きの子どもが悪いのではない。お金さえ出せば何でも手に入る世界を作り出しているのは、商魂たくましい大人なのだ。世界で一番力の強い「ヘラクレスカブトムシ」は子どもたちには手の届かない憧れの存在のままであったほうがいいのに。
子どもには、夢のままで心に持ち続けておいたほうがよいものがたくさんある。心の中で大きく膨らませ、思い出すたびにわくわくする。欲しくてたまらなくても、手には入らない。そういうものが多くあったほうがいい。いや、子ども時代には、ほとんどが手に入らないままでよい。何でも欲しいものは手に入る、手に入れてしまう。そんな習慣が、不幸な事件にもつながってしまう自己中心的な人間を作り上げてしまうのではないだろうか。
先日、調べ物をしていたらとてもすばらしいものを見つけた。「子どもの養育十戒」と名づけられた子育ての教訓である。
「 子どもの養育十戒」(The Needs of Children)
<Kelmer Pringle提唱,津崎哲雄訳>
第一戒 子どもには、連続し首尾一貫した愛情ある養育を与えよ。これは、食物が身体にそうであるように、子どもの心の健康にはなくてはならないことである。
第二戒 自分の時間を溢れるほど注ぎ、子どもを理解しようと努めよ。一緒に遊んだり、本を読みきかせたりすることは、家庭をこぎれいにしたり、きっちり片付けたりすることより、はるかに重要である。
第三戒 絶えず子どもに新たな経験をさせ、溢れるほど言葉かけを行なえ。そうした働きかけは、子どもの心の豊かな成長に不可欠である。
第四戒 探検したり、模倣したり、組み立てたり、ごっこ遊びをしたり、創造したり、あらゆる方法で子どもが一人遊び、他の子どもとの遊びの両方を行なうよう奨励せよ。
第五戒 なし遂げたことより、なし遂げようと努力したことの方を余計にほめよ。
第六戒 子どもが果たす責任(仕事)を次第に増やしてゆけ。あらゆる技能と同様、責任(仕事)を果たすには実際にそれを行なわせることが必要である。
第七戒 すべての子どもはユニーク(固有の存在)であることを忘れるな。ゆえに、ある子に相応しい取扱い方が他の子どもに通用するとは限らない。
第八戒 子どもに「だめ」と言う場合は、その子の気性、年齢、理解度に相応しく伝えよ。
第九戒 もうおまえを愛するのはやめるとか、おまえを手放すとかいうような脅しを絶対に行なうな。子どもの行動を拒否することはかまわないが、子ども自身を拒否するというような言動は絶対に慎め。
第十戒 子どもから感謝を期待するな。子どもは自ら誕生を望んだわけではなし、産む選択は親がなしたのであるから。
「親として、どれほどの時間を子どものために費やしていますか? どれほどの言葉がけを行っていますか? 子どもの力を信じ、それを伸ばすための力添えを怠っていませんか? 親の都合で子どもたちの心を傷つける言動はしていませんか?」 きっとどのお父さんやお母さんも一つや二つは「ギック」とするところがおありだろうと思う。この十戒の中にも、欲しいものは手に入れるとか、物質的に満たしてやることには一言も触れていない。子どもの心を育てるのは、ものの豊かさではないのだ。
さて、最後に、子どもたちの虫ブームが、巻き起こしかねない心配事を書いておこう。それは、現地のみならず日本の生態系を崩す恐れがあるということである。今ザリガニと言えば真っ赤なアメリカザリガニばかりであったり、目にするほとんどのタンポポがセイヨウタンポポであったりするように、日本のカブトムシやクワガタムシが外国産のものに取って代わられてしまうことだってあるのだ。熱帯の草花が路地で冬を越せるくらい温暖化が進んでいる。逃げ出した虫が日本で繁殖することは十分考えられる。こんな地球規模の大問題の責任を大人たちはどう考えているのだろうか。少なくとも買ってきた虫たちを、かわいそうだからと、外に逃がしてやる行為は絶対にしないようお子様に話していただきたい。
平成17年8月号 隣の芝生 足元の芝生
「今進めている行政改革は、ぜひ教育改革から」ということが最近耳に入ってくることが多くなった。「未来を担う子どもたちにこそお金を使うべきだ」と町民の皆さんが教育問題に関心を持ち、
その一つとして、子どもたちは、「学校、家庭、地域」で育てると言う大原則を実現することがある。いままで、「学校・家庭・地域」の連携は叫ばれていても実はしっかりとした協力体制はできていない。それどころか保護者は「子どものことは学校にお任せ」あるいは「言いたいことは山ほどあっても学校には何もいえない」。学校の先生は「家でもっときちんと子どもを見てよ」「親は自分のこのことしか見ていない。勝手な苦情ばかり言わないで」などという、学校と家庭の見えない壁の存在は一向に消えない。そこで、めざすのは、「親の思いが届く学校」を作ること。保護者の願いを、先生たちの専門的な立場で実現すること、実践に当たっては、保護者も教員とともに手を携えて子どもの指導に当たること、そのシステム作りである。3年計画でいきたい。
さて、タイトルの「隣の芝生、足元の芝生」のことであるが、「教育改革を」という声が、「お隣の市では毎日のように教育のことが新聞に載っているのに、わが町は何もやっていないじゃないか」という思いから出ているらしいことに少々残念な気持ちを隠し得なかったので、あえて書かせていただいた。
確かにお隣の市では、新しい教育の姿をめざして積極的に取り組まれ、外に向かっての発信にも力を注いでいる。確かにすばらしいことである。しかし、それら
また、比較する材料がないと分からない
では、子どもたちは?と言えば、心身ともに健やかに子どもたちが育っている事実、これほど胸を張って自慢できるものはない。
先日ある会で、他の市に非常勤で教員をされている方からお話を伺った。その方はこう言われた。「
教育とは派手である必要はない。今改めるべきところは勇断をもって改め、地道に、着実に、足元に育っている元気な芝生をもっともっと力強く育てていくことが大切である。
平成17年7月号 他人への迷惑は自分は気づいていない
ただでさえ気分が重くなる雨の日の通勤。ちょっとした心配りがあればなあとため息が出てしまうことがしばしばある。
まずは、たたんだ傘の持ち方について。柄の先を持って真下に下げていただければ何の問題もないが、先を後ろにして斜めに持つ人がいる。階段を上るときそんな人の後ろについたら大変である。体の動きに合わせて前後に振れる傘の先が、私めがけて襲いかかるのだ。その人にとっては、傘の先は膝頭の高さであっても、2・3段下にいる私には胸の辺りになる。中には、傘の中ほどを握り、水平に近い角度で持ち運んでいる人もいる。こうなると胸どころか顔面に直撃を食らいそうで、恐怖心はいっそうつのる。人ごみで横へ移動することもできない朝の駅の階段となれば否応無しに、上りきるまで恐怖の傘のお供をさせられることになってしまう。
次なるは、私を悩ませる濡れた傘。電車が揺れるたびに私の手にべたっとした感覚が伝わってくる。隣に立っている人の傘がそこにある。混み合った状況では仕方がないとは思うが・・・。私は、スーパーマーケットなどの入り口においてあるビニルの傘袋を捨てずに、傘の内側の骨に結び付けておき、濡れ傘をたたんだときは、必ずそれを利用するようにしている。短く結んであるビニル袋は、傘をひらいていてもたたんでいても外からは見えない。濡れた傘で他人様に迷惑を掛けることもなくなるし、車のときも床や座席シートを濡らさなくてすむ。一度使って「ポイ」では傘袋も可愛そうだ。資源を大切にしよう。
さて、次は、人の動きだ。ホームで電車を待つ人。どうしてもう少し整然と並んで待つことはできないのだろう。ホームにあふれるほどの人数であればいたしかたないが、そうでなくても電車を待つ人は、結構歩きにくい状況を作っている。朝の犬山駅は、絶対にホーム上をまっすぐには歩けない。少し歩いては右へ左へと人をよけながら進まなければならない。新幹線のホームのように白線が引かれてあれば多少は解決できるかもしれないが、利用電車がまちまちの乗客でごった返す名鉄のホームではそれも無理だろう。一人ひとりのマナーに期待するより仕方がないようだ。
電車がホームに着きドアが開くと同時に中へ人が吸い込まれていく。私が小さかった頃よく目にした我先にという醜い姿はさすがなくなったが、まだ客が降りきらないうちに乗り込む人がいる。日本人の乗降マナーはまだまだかな。
前の人に続いて電車に踏み入れたとたん、前の人の背中にぶつかり、ホームへ戻されそうになってしまうなんてことが時にはある。満員電車なら、こちらから体当たりをするような心構えで乗り込むからそんなことはないのだが、結構すいている電車だから、予想もつかない前の人の行動に翻弄されてしまう。「どうしてこんなところで立ち止まるんだよ。」 どうやら乗り込んだ瞬間、右へ行こうか、左へ進もうか歩みを止めて状況を読みとっているらしい。「おいおい、自分さえ乗ってしまえば安心なのかよ。まだまだたくさんの人が乗ろうとしているんだよ。せめて反対側のドアまで進んでからにしてよ。」
ちょっとした不愉快な気分を味わっているのは私だけではないはずだ。ご本人たちは気づいていないようだから教えてあげるべきなのだが見も知らぬ他人にはそれができない。勇気のない自分が情けない。残念!
知らないうちに他人に不愉快な思いをさせている、迷惑をかけている。私だって例外ではないはずだ。私がそうであるように、誰も私に注意してくれない。慢心はいけない。気をつけなければならない。誰も何も言ってはくれない立場であればあるほど、改めるべきところがないか常に謙虚に自分自身で振り返えらなければならない。これは自分自身への戒めであるが、同じような心がけをして欲しいと思う事例が先月あったばかりだ。
それは「
新聞社は「
「ペンは武器である」。どんなに正しい使い方をしていると認識していても、ひょっとしたら傷ついている人もいるかもしれない。私の毎月のこのページで不愉快な思いをしている人がいるかもしれない。注意。注意。